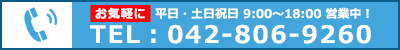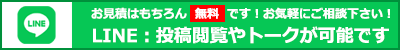先日、東京・千代田区の樋口高顕区長は、住宅価格の高騰に対抗するため、5年間の転売禁止や、同一名義での複数物件購入禁止を業界団体に対して要請しました。
東京の人気エリアでは、住宅価格が急激に上昇し、一般的な年収の人が手の届く価格帯を超えてしまっており、こうした現状を受け、行政が価格高騰を招く投機行動を抑制するための対策を講じることはおおむね好意的に捉えられているようです。
しかし、現時点ではあくまで「要請」に過ぎず、強制力はないので、そのため、実際の効果には疑問が残り他区の取り組みも含めて効果測定として注視が必要です。
これまで投資利回りが3%台であっても積極的に都心物件を購入していた投資ファンドにとって、調達金利の引き上げは、当然ながら期待投資利回りを引き上げて考える必要が出てきます。
通常投資利回りの善し悪しを判断するには、ベースレートとなる絶対安全といえる投資対象の利回り、例えば国債レート(10年物など)を基準に置きます(2025年5月時点で年1.525%)。そのうえで、どれくらいのリスクを覚悟するか(リスクプレミアム)を上乗せして、投資利回りを決定します。
政策金利は、短期プライムレート(銀行などが設定する最優遇取引先に対する1年未満の貸出最優遇レート)に連動しています。つまり調達レートが上昇することは、投資にあたってのマーケットリスクが高まることを意味しています。
これまでは3%前半でもOKだった投資にさらなるリスクプレミアムを乗せる必要があるかを投資家は判断しなければならなくなるわけです。要求する期待投資利回りが上がれば、その分購入価格を下げるか、物件から得ることができる賃料収入が上がるという前提が必要になります。
社会がインフレの状況になって賃料がうなぎ上りになっていけば、物件価格は下がらずに新たに設定した投資利回りを確保できますが、賃料が期待通りに上がらない場合は、投資目線(金額)を下げていかなければならなくなります。2025年以降の不動産マーケットはこの状況を見極める状況にあります。
大企業を中心として年収は上がる傾向です。人手不足は全業界共通なので、企業は優秀な人材を確保するためには給与引き上げのみならず、社宅など福利厚生費の充実が求められるようになっていきます。そうした意味で賃貸マンションの賃料は今後の上昇が期待できる状況にあります。
ただし、既存の賃貸住宅のテナント賃料がただちに上げることができるのかと言えば、日本の借地借家法は、借手側に非常に有利な設定になっています。
家賃の引き上げを大家が要求しても、テナントがこれを拒否(現状の賃料であることを主張)した場合、大家側は賃料引き上げについて合理的な理由を提示し、テナントの納得をもらわない限り、値上げを実現できません。つまり、家賃上昇が世の中広くに定着していくにはかなりの時間がかかるということです。
またオフィスは日本国内でも完全なリアル勤務に戻る会社があるいっぽうでハイブリッド型の働き方はこれからの時代の標準になる可能性が高いといえるでしょう。その意味では更なる賃料の引き上げにはおのずと限界があることになります。
ということは今後、高くなっていく期待利回りに対して、現状の物件利回りが上がる可能性が少ない、つまり価格は頂点にすでにあることを意味しています。買い手がいない限り、価格は下がらざるを得ません。バブルの崩壊は意外と近いのかもしれません。
データで見ると特に相場を上げているのは、東京都の港区、中央区、千代田区の3つのエリアになり、新宿、渋谷が追従している状態で、環七エリアになると、コロナ以降、横ばいを推移しています。
弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、
空室対策、不動産管理、地震保険や補助金助成金申請サポート、各専門の士業の御紹介などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしております。
相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
https://meiseitosou.com/contact/