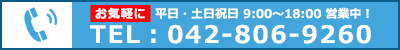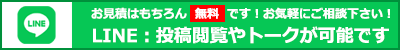大規模修繕工事を行う場合、外壁がタイルだと劣化枚数によって工事金額が大幅に変わってくるため、工事計画を行う上で現状把握が非常に重要になります。
従来の方法では、お見積りをする段階で1階部分のみ、打診調査を行って1階の外壁面積に対して劣化(浮きや割れ)している箇所を洗い出し、全体的に同じ割合で「概算見積書」を作成して契約、そして工事が始まり足場を建ててから全体の調査を行って契約した数量と照らし合わせるのが一般的でした。
最近ではドローンを使用して、予め浮きや割れなどを確認する方法を取り入れている方もおられます。
但し、ドローンを使用しての調査は以下の問題点があります。
➀ベッドタウンでないと、周辺建物との距離がなく飛ばすことができない。
➁赤外線カメラを使用しても、タイルの浮きが何となく分かっても具体的な枚数や補修方法が判断ができず、交換なのかエポキシ注入で済むのか、それとも施工をする必要がないのか判断ができない。
③北面においてはドローンの精度が低くなり、結局、概算の見積りに終始する。
④ドローンの調査費用も発生する。
そんな中、弊社が取り入れている無足場工法であるロープアクセスによる打診調査を行うと➀から③の問題が解決します。
また費用もドローン調査と、ほぼ同額にて行えるにも関わらず、具体的な補修方法と、それに沿った補修枚数がそれぞれ明確になる為、工事計画に非常に有効です。
■具体的に有効な工事計画とは
➀タイルの枚数が確定するため、あとから追加工事が一切発生しない。
➁資金調達に時間をかけることができ、工事中に追加でお金を工面をする必要がない。
③タイルの必要数を特注で事前に2ヶ月前より制作をすることができるので、張り替えた箇所が目立たず美観を維持することができる。
実際に無足場工法であるロープアクセスで調査をしている様子です。
このようにタイルを1枚ずつ確認をしていきます。
契約をして足場が建ってしまうと、施工会社の言いなりになる場合があります。
➀足場を建ててから調査を行ったら、想定よりも劣化している箇所が多くて追加で〇百万円かかります。
➁すぐに工事費用を用意しないと足場の設置期間が延びることで追加で足場のリース代が発生します。
③想定通りの劣化枚数でした!(本当は想定よりも少なくても利益として取る会社も一定数いると思われます)
■明誠のメリット
弊社では事前に調査をした上で、お見積書を作成させて頂きますので、いい加減な調査を行い、実際に工事が始まってから劣化箇所が多かった場合、全て自分たちに返ってきてしまうので、自社を守るためにも1枚ずつ丁寧に調査を行います。
大きな金額になる工事ですので、しっかりとした計画と、悪い業者に騙されないことが非常に重要になります。
弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、
空室対策、不動産管理、地震保険や補助金助成金申請サポート、各専門の士業の御紹介などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしております。
相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
https://meiseitosou.com/contact/
■打診調査とは??
-
**打診調査(だしんちょうさ)**とは、外壁(タイル、モルタル、石材など)を専用の打診棒やテストハンマーなどで軽く叩き、そのときに生じる音(あるいは感触)の違いを聞き分けることで、「健全部」と「浮き/剥離/中空部」の有無・範囲を判断する方法です。bureauveritas.jp+3drone-frontier.co.jp+3日本耐震診断協会+3
-
通常、目視調査・触診調査などと組み合わせて実施され、表面からは判別しづらい“隠れた異常”を発見する手段として重視されます。buil-repo.com+2drone-frontier.co.jp+2
-
手が届かない高所部分では足場、高所作業車、ロープアクセス(降下作業)などを併用して調査します。Takaoプランニング株式会社 |+3株式会社ギアミクス+3大阪のビル・マンションのメンテナンス・清掃なら八翔ビル管理株式会社+3
-
打診で異常が疑われた箇所については、さらに赤外線調査や詳しい補修調査を行う手法も併用されます。drone-frontier.co.jp+2bureauveritas.jp+2
このように、打診調査は「非破壊で、比較的シンプルな器具と技術で、内部の浮きや剥離を探る」調査方法として、外壁診断の中心的な手段の一つとされています。
2. なぜ打診調査が重要なのか:目的・意義
外壁打診調査を行うことには、以下のような複数の目的と意義があります。
2.1 安全性確保:落下事故・人的被害の防止
-
建物の外壁が劣化してタイルやモルタルが浮いている・剥離している状態を放置すると、それらの外壁材が脱落・落下するリスクがあります。歩行者・近隣住民・建物利用者に危害を及ぼす重大事故につながりかねません。ALSOK(アルソック)+3buil-repo.com+3bureauveritas.jp+3
-
特に、道路沿いや歩行者通路上を覆うような外壁の上部・庇・バルコニー・外壁の張り出し部などは、落下リスクが高いため優先的に点検対象になります。Takaoプランニング株式会社 |+2bureauveritas.jp+2
-
早期に異常を発見して補修措置をとることで、重大事故を未然に防ぐことができます。bureauveritas.jp+3ALSOK(アルソック)+3大阪のビル・マンションのメンテナンス・清掃なら八翔ビル管理株式会社+3
この「人的被害の防止」は、調査を実施する最も根本的・本質的な意義と言ってよいでしょう。
2.2 建物の機能性維持・水害予防
-
外壁の浮き・剥離は、隙間から雨水や湿気が浸入する経路になります。外壁材と躯体(コンクリート、下地)間に水が入ると、下地の劣化、コンクリートの中性化進行、鉄筋のさび、内部の空洞化などを促進させます。kiku-tech.com+4日本耐震診断協会+4drone-frontier.co.jp+4
-
ひび割れや目視で確認できる異常以上に、打診調査では隠れた劣化領域を探し出すことができます。目視だけでは判断できない“内部の浮き”や“隠れた中空部”を検知できる点が、打診調査の大きな強みです。drone-frontier.co.jp+2bureauveritas.jp+2
-
水の浸入が建物内部に及ぶと、断熱性能や気密性能も劣化し、建物全体の居住性や性能が低下するおそれがあります。
2.3 資産価値維持・長寿命化・修繕コストの抑制
-
適時の調査・診断を行えば、劣化が軽微なうちに修繕できます。これによって、大規模な補修・改修を回避でき、結果的に修繕コストを抑える可能性があります。ALSOK(アルソック)+3buil-repo.com+3bureauveritas.jp+3
-
建物の外観状態や健全性は、不動産価値・賃料価値にも影響を与えます。劣化が進んだ外壁は見た目も悪く、資産としての印象を悪化させる可能性があります。ALSOK(アルソック)+1
-
定期的な外壁点検・予防保全を行うことにより、建物を“使える状態”に保ち続け、寿命を延ばすという観点からも重要です。
2.4 法令遵守・報告義務対応
-
日本では「建築基準法」や「建築基準法施行令」などの規定により、特定建築物(一定規模以上または用途を持つ建物)については、定期的な外壁点検・報告が義務付けられています。大阪のビル・マンションのメンテナンス・清掃なら八翔ビル管理株式会社+3bureauveritas.jp+3ALSOK(アルソック)+3
-
具体には、全面打診等調査を10年に1度行うことが定められています。Takaoプランニング株式会社 |+3bureauveritas.jp+3株式会社テックビルケア+3
-
外壁改修後10年を超えた場合や、前回の全面調査から10年を超えた場合には、報告義務が発生します。ALSOK(アルソック)+2bureauveritas.jp+2
-
このような義務を怠ると、行政から是正を求められる、罰則が科される、建築物使用停止命令となる可能性もあります。ALSOK(アルソック)+1
したがって、打診調査は法令対応上も必須の手段となっています。
3. 打診調査の手法・実施形態とその特徴
次に、打診調査をどのように実施するか、その手法と特徴を整理します。
3.1 調査実施手段
打診調査には、主に以下のような実施手段(アクセス手段・調査体制)が用いられます。
| 方法 | 概要 | 長所 | 短所/注意点 |
|---|---|---|---|
| 足場設置 | 外壁全体に仮設足場を組んで作業 | 調査員が壁面近接可能、目視と打診併用しやすい | 足場設置・撤去に時間・費用がかかる |
| 高所作業車/ゴンドラ | 車両やゴンドラで外壁にアクセス | 足場不要、ある程度迅速に調査可能 | 建物高さ・周囲状況に制約、道路占有許可が要ることも |
| ロープアクセス/降下作業 | 屋上からロープを垂らして調査員が降下しながら打診 | 足場不要、コスト抑制、狭所対応可 | 調査者の安全確保が必須、技術と経験が問われる |
| 部分的打診 + 目視併用 | 目視で異常を探し、疑われる箇所に絞って打診 | 効率的、コスト抑制 | 見落としリスク、全面把握に不向き |
これらの方法は、建物規模・形状・立地条件・予算・安全性要件などを勘案して使い分けられます。ロープアクセス専門|無足場の高所作業は4Uにおまかせ!+5株式会社ギアミクス+5j-assess.co.jp+5
近年では、赤外線調査+打診調査を組み合わせて効率化を図るケースも増えています。赤外線調査により浮きの可能性が高い領域を事前に絞って、打診を重点的に実施する方式です。株式会社テックビルケア+3drone-frontier.co.jp+3drone-frontier.co.jp+3
3.2 調査判定の原理と限界
-
健全部を打診すると、澄んだ「カン・コン」といった乾いた音が返りますが、内部に空洞・浮きがある部分を打診すると、「こもった音」「鈍い音」「濁った音」などの異なる響き方になります。調査者はその音の違いを経験と感覚で判断します。drone-frontier.co.jp+3note(ノート)+3リフォームジャーナル+3
-
ただし、判定は調査者の経験・技術・聴覚に左右されるという欠点があります。熟練度や判断基準が異なると、判定精度にばらつきが出る可能性があります。drone-frontier.co.jp+2bureauveritas.jp+2
-
また、打診できない部位(極端な高所・障害物のある場所など)や表面が粗すぎる下地では、音の判別が困難な場合があります。
-
打診調査単体だけでは、中空部の底部形状や全面除去可能性、剥離面の接着強度までは把握できないため、必要に応じてさらなる補助調査(微破壊試験、走査型赤外線、赤外線サーモグラフィなど)を併用することが望まれます。drone-frontier.co.jp+2bureauveritas.jp+2
4. 打診調査を怠る・遅らせるリスク
打診調査や定期点検を怠ったり、著しく遅らせたりすると、以下のようなリスクが発生します。
4.1 事故リスクの顕在化
浮きや剥離部材が落下して 歩行者・利用者への被害を生じる可能性。特に風や地震で揺れが生じると、劣化した外壁材が外れることがあります。ALSOK(アルソック)+3buil-repo.com+3bureauveritas.jp+3
4.2 修繕・補修費用の急激な上昇
初期段階で補修できたはずの部位を放置しておくと、劣化が進展し、壁全体の張り替え、下地補修、躯体補強など大規模な工事に至る可能性があります。その結果、修繕コストが飛躍的に高くなるリスクがあります。高所安全対策のスペシャリスト!常設型転落防止システム「アクロバット」+3buil-repo.com+3リフォームジャーナル+3
4.3 構造体への悪影響・寿命短縮
外壁からの水が躯体に浸入し、コンクリートの中性化、鉄筋の腐食、クラック拡大、断熱材の劣化などを誘発することで、建物自体の耐久性や長寿命性を損なう可能性があります。
4.4 不動産価値の低下・賃料低迷
劣化・ひび割れ・浮きなどの外観不良は、建物の印象を悪化させ、不動産評価を下げる要因になります。賃貸物件であれば入居者離れを招くこともあります。
4.5 法令違反・行政対応リスク
定期報告制度に違反したり、報告を怠ったりすることで、行政から是正命令を受けたり罰則が科されたり、最悪の場合、建築物使用停止命令といった措置を受ける可能性があります。ALSOK(アルソック)+2bureauveritas.jp+2
こうしたリスクを避けるために、定期的な打診調査が不可欠というわけです。
5. 打診調査を適切に行うポイント・注意点
打診調査を効果的かつ安全に行うためには、以下のポイントに注意すべきです。
5.1 調査者の技術・経験の確保
-
音の違いを聞き分け、正確に判定できる熟練技術者を起用すべきです。経験の少ない調査者では誤判定のリスクが高まります。drone-frontier.co.jp+2bureauveritas.jp+2
-
調査員には音響学的な訓練や定期的な技術研修を行うなど、スキル向上策を講じるべきです。
5.2 適切なアクセス手段の選定と安全対策
-
足場設置・高所車両・ロープアクセスなど、建物構造や周囲環境に応じた最適なアクセス方法を選ぶ必要があります。株式会社ギアミクス+2大阪のビル・マンションのメンテナンス・清掃なら八翔ビル管理株式会社+2
-
調査中の落下・墜落事故を防止するため、作業員の安全装備、墜落防止設備、適切な安全管理体制(命綱、生命線、救助体制など)が必須です。高所安全対策のスペシャリスト!常設型転落防止システム「アクロバット」+2Takaoプランニング株式会社 |+2
-
天候(強風、雨、雷など)や作業時間帯の選定にも注意を払うべきです。
5.3 調査範囲・頻度の設定
-
建物の形・用途・周囲環境に応じて、重点点検箇所を決め、適切な範囲で調査を行うことが効率化の鍵です。リフォームジャーナル+3Takaoプランニング株式会社 |+3bureauveritas.jp+3
-
定期的な点検周期を定め、打診調査(部分的または全面)を行うこと。法令上では10年に1度の全面打診が求められています。ALSOK(アルソック)+3bureauveritas.jp+3株式会社テックビルケア+3
-
目視調査や赤外線調査などを併用し、打診調査を効率的に実施するクセをつける。赤外線調査で摘出した異常候補箇所を先行して打診する手法が有効です。drone-frontier.co.jp+2drone-frontier.co.jp+2
5.4 記録・報告・補修連携
-
調査時には、異常箇所の位置・範囲・打診音の判定内容・写真・マーキング記録を残すべきです。これにより、後日の比較・進行把握・補修計画立案が容易になります。
-
調査結果を基に、補修が必要な箇所を分類(軽微補修・中規模補修・全面改修)し、補修スケジュールを立案します。
-
法令報告義務がある建物については、調査結果を所定様式で報告書としてまとめ、関係行政機関へ提出する必要があります。bureauveritas.jp+1
-
補修工事とは一体として計画することが望ましい。調査時にマーキングされた異常箇所をそのまま工事班に引き継げるよう、調査段階から補修を見据えた設計で進めるべきです。
6. 実際の運用・導入の視点:成功要因・課題
打診調査を建物管理・維持保全の一環として効果的に運用するためには、以下のような視点も重要です。
6.1 コスト対効果のバランス
-
打診調査自体は比較的低コストな手法ですが、足場設置や高所アクセスのコストがかかることもあります。限られた予算内でいかに効率よく実施するかが鍵となります。
-
赤外線調査やドローン併用、部分打診+重点打診などのハイブリッド方式を採ることでコストを抑えつつ精度を確保するケースが増えています。ALSOK(アルソック)+3drone-frontier.co.jp+3株式会社テックビルケア+3
-
調査と補修を同時に計画・実施する(調査足場を補修にも使う、調査マーキングを補修図面に活用する)ことでロスを減らす工夫が有効です。
6.2 継続的管理・劣化モニタリング
-
一度調査して終わり、という運用では不十分です。複数回(数年単位で)調査を重ね、劣化の進行状況をモニタリングすることが望まれます。
-
調査記録(過去データ)と比較して劣化進行の速度を把握すれば、次回の補修計画や長期修繕計画(ライフサイクルコスト)立案にも資する情報が得られます。
6.3 調査体制・業者選定の慎重さ
-
打診調査を正確に実施できる業者を選ぶことが極めて重要です。実績・技術・保険・安全体制などを確認すべきです。高所安全対策のスペシャリスト!常設型転落防止システム「アクロバット」+3buil-repo.com+3bureauveritas.jp+3
-
業者が自社で足場や高所機材を持っているか、ロープアクセス技術を持っているか、安全管理体制がどうなっているか、調査結果の報告精度やドキュメント能力などを見極めるべきです.
-
調査計画段階で、建物図面(設計図・竣工図・改修履歴)を提供し、それに基づいて調査方針を協議することが望ましいです。
6.4 技術革新への対応
-
最近では、赤外線サーモグラフィ(ドローン搭載型含む)・レーザー計測・三次元モデリング・インフラIoTセンサー(振動・音響センサー等)など、新しい技術の導入が進みつつあります。kiku-tech.com+3drone-frontier.co.jp+3ALSOK(アルソック)+3
-
これらを打診調査と組み合わせることで、効率化・広域把握・精度向上を図れる可能性があります。ただし、技術導入にはコストや運用ノウハウが要求されるため慎重に検討する必要があります。
7. まとめと提言
以上を踏まえると、外壁打診調査は、建物の安全性確保・機能維持・資産価値維持・法令遵守を実現するうえで欠かせない施策です。特に以下の点が重要です:
-
定期的な調査実施
法令義務・安全確保の観点から、全面打診を含む調査は10年に1度、または異常が認められた部分を重点に部分打診を含めた定期点検を行うべきです。 -
熟練技術者による判定と記録
調査者の経験と技術が判定精度を左右するため、信頼できる技術者・業者を選定し、調査記録を詳細に残すことが重要です。 -
効率的なアクセス手段と安全確保
足場・ロープアクセス・ゴンドラ等を適切に使い分け、安全体制を確立した上で調査を行うべきです。 -
補修との連動計画
調査段階で異常箇所のマーキングや補修計画を設計に織り込んでおくことで、補修コストを抑制できます。 -
技術融合の活用
赤外線調査・ドローン・センシング技術等を適時取り入れ、打診調査を補完することで、調査効率と精度を向上させられます。 -
長期維持管理・モニタリング視点
複数回の調査結果を比較して劣化進行を把握し、中長期的な建物維持戦略(ライフサイクルコスト管理)に活かすことが望まれます。