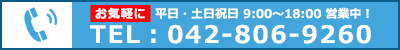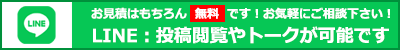11月も中盤に差し掛かり、朝晩の冷え込みが出てきましたね。
実は以外と知らない大規模修繕工事に役立つ豆知識を御紹介します。
それは、氷点下になるとコンクリートのヒビ(クラック)が入りやすいんです!
その為、ロープアクセスによる外壁調査は1~3月頃に行うことがおススメです。
1.冬にコンクリートがヒビ割れしやすい理由
冬場にコンクリートにヒビが入りやすくなるのは、主に「温度・湿度の変化」「水分の出入り」「材料・施工条件」「構造・外的負荷」という複数の要因が重なるためです。以下、主要なものを整理します。
(1) 凍結‑融解サイクル(Freeze–Thaw Cycle)
冬場で最も典型的な原因の一つが、コンクリート内部や表面に浸入した水分が凍ったり解けたりを繰り返す「凍結‑融解」サイクルです。
コンクリートは見た目には固体ですが、微細な孔(ポア)やクラック、毛細管が多数あります。そこに水分が入ります。
Procon 24/7
+2
House Digest
+2
気温が0℃以下になると、その水分は氷になり、体積が約9%程度増加すると言われ、その結果、内部に大きな圧力がかかります。
Procon 24/7
+1
氷が解けることで水に戻り、氷があった場所に隙間・クラックが残ってしまい、次の水分侵入や氷化の機会を増やします。
Procon 24/7
+1
これが何度も繰り返されると、微細クラック→明確なクラックへと進展します。
House Digest
+1
この現象は外部に露出したコンクリート、寒暖差・湿気変化が大きい環境では特に顕著です。
(2) 水分侵入・凍結による構造的応力および劣化
冬場には降雪・凍結・融雪水などによって、水/湿気がコンクリート表面および内部に浸入しやすくなります。
表面・目地・クラック等からの浸水があると、凍結サイクルだけでなく、「水分の出入りによる収縮・膨張」「凍結による剥離・スケーリング(剥がれ・ピット化)」が起きます。
a1concrete.com
+1
また、凍結融解だけでなく、融雪剤(塩化剤)を使用することで、コンクリート内部の塩分浸入・凍結融解耐性劣化などを引き起こすこともあります。
Port Aggregates
+1
そのため、冬期環境では水分管理(侵入・排除)・凍結耐性という点が非常に重要になります。
(3) 温度変動・乾燥収縮・熱応力
冬という季節背景では、日中・夜間あるいは屋外・屋内での温度変動が大きくなりがちです。
コンクリートは熱を受けると多少膨張し、冷えると収縮します。この繰り返しは「温度変動応力」をコンクリートに与えます。
Polycote
+1
特に寒さ・乾燥条件下ではコンクリート内部の水分蒸発・乾燥収縮が進む可能性があります。この「乾燥による収縮」も微細なクラック発生要因になります。
arXiv
+1
冬期に施工・硬化が進むコンクリートでは、セッティング・硬化が低温により遅れ、初期強度が十分出ていないうちに変形・応力を受けるとクラックが発生しやすいという報告もあります。
fascrete.com
(4) 施工・材料条件の影響
冬場の環境下で施工される、または冬を迎える建物のコンクリートでは以下のような材料・施工上の弱点がクラックの発生を助長します。
コンクリートの常水セメント比(w/c比)が高め、あるいは寒冷時に適切な空気連行・凍結耐性を持たない配合である場合、凍結‑融解に対して脆弱になります。
Polycote
控えめに言っても、冬場に打設し、硬化中に凍結したコンクリートは、氷の形成・脱水・遅れ硬化などによりクラックが入りやすいという報告があります。
fascrete.com
目地やコントロールジョイント(伸縮目地)が適切に設けられていないと、温度変化・乾燥収縮に対して応力が逃げず、「ランダムなひび割れ(ラッピング割れ)」が発生しやすくなります。
Polycote
+1
基礎・下地・支持地盤の施工精度が低い(たとえば凍結融解サイクルにより地盤が動きやすい環境)と、コンクリートに応力や変位が加わることでクラックが発生しやすくなります。
Procon 24/7
(5) 維持管理/点検が十分でないことの影響
冬場には雪・氷・凍結水などが影響を与えるため、日常的な点検・早期発見・補修が遅れると、微細なヒビが冬の作用により急速に拡大するケースも少なくありません。
例えば、小さなひび割れから水が入り、凍結膨張で更に拡大――という流れは典型です。点検が甘いと、見逃しがちになります。
Port Aggregates
+1
以上のように、「冬だからヒビが入りやすい」というのは単一の原因ではなく、複数の環境条件・施工条件・維持管理条件が重なった結果です。特に、外壁・高所・屋上・開口部まわり・凍結水が回りやすい構造部分などでは注意が必要です。
2.点検の重要性
では、このようにヒビが入りやすい条件がある中で、なぜ点検が重要かを整理します。ヒビ割れを早期に発見・診断・補修することには以下のようなメリットがあります。
(1) 早期発見・被害の拡大防止
小さなヘアークラックや初期のクラックの段階で発見すれば、浸水・凍結・膨張・剥離など二次的な損傷に進む前に対処できます。
もし点検を怠ると、冬の凍結‑融解サイクルでクラックが急速に進展し、補修費用や改修費用が大きく増大することがあります。例えば、表面のひび割れを放置したまま翌春に剥離・欠損・鉄筋露出などに至ると、構造的な安全性にも関わる可能性があります。
お客様(ビル・ホテル・マンション・プラントなど)にとっては、工事コスト増、運営業務や利用者への影響、あるいは管理組合であれば資産価値低下というリスクも出てきます。
(2) 構造・耐久性確保/資産価値維持
ヒビ割れが進行すると、コンクリートの耐久性低下(鉄筋腐食、ひび割れ内部からの水・塩化物侵入など)を招きます。例えば、耐久性研究では「コンクリート劣化=水分侵入が主要因」という指摘があります。
ウィキペディア
+1
建物を長期間安全・安定に運用するためには、定期的な点検・診断・補修が不可欠であり、特に冬を迎える前・冬明け直後の点検が効果的です。
また、資産運用・収益物件(ホテル・マンション)では、見た目の劣化・外壁損傷などが利用者の印象や稼働率にも影響を及ぼす可能性があります。外壁・共用部のひび割れを放置すると「古びた印象」が強まり、資産価値・ブランド価値にも響き得ます。
(3) コスト制御・修繕計画の立案
初期段階での点検・補修は、後に発生しうる大規模改修(全面足場・解体・再施工など)を未然に防ぐことができ、トータルコストを抑える戦略の一部です。
冬場に特化した劣化モード(凍結膨張・雪水浸入・塩害など)を把握し、点検時にそれらを重点チェックすることで、修繕計画を季節サイクルに合わせて合理的にスケジューリングできます。例えば、冬前に目地・クラックを補修し、水の浸入を防いで凍結ダメージを抑えるという流れです。
さらに、建物運営・設備管理(ホテル稼働率・マンション共用部管理)と連動させたメンテナンススケジュールを組むことで、無駄な仮設足場やロープアクセス費用を抑えることも可能になります(特に、貴社のように「足場+ロープアクセス」併用提案ができる立場では、点検結果を踏まえた最適工法の選定が重要です)。
(4) 安全性・法令遵守・管理責任
建物外壁や屋上、共用構造部にヒビ割れがあると、そこから剥落・漏水・鉄筋露出などの安全リスクが生じます。管理組合・オーナーとしては定期点検義務や安全配慮義務を果たす必要があります。
また、ひび割れから漏水が発生し、構造体の腐食を招いた場合、将来的な損害賠償・保険請求の問題にもつながりかねません。その意味でも点検は「コスト」ではなく「リスク管理」の一環と捉えるべきです。
冬季を前に点検を行い、「次の冬にどこを重点的に見ておくか」を整理しておくのは、建物管理における先手の対策です。
3.防止策(冬場を迎える・冬期中・冬明け後)
では、冬場のひび割れを未然に防ぐための具体策を、施工段階・運用段階・点検・補修段階それぞれに分けて整理します。なお、貴社のように「足場+ロープアクセス」「保険申請代行」「ドローン調査」など外装改修サービスを提供されている企業であれば、お客様に「なぜこの時期にこの処置をすべきか」をご説明するためにも役立ちます。
(A) 施工・改修段階における防止策
適切なコンクリート配合・空気連行設計
特に冬季・寒冷条件にさらされる外壁・屋上などでは、「凍結融解抵抗」「空気連行(微細な気泡を入れる)」が有効です。
Polycote
+1
水セメント比(w/c比)を抑えて、過剰な水分が残らないように配慮すること。水分過多だと収縮・クラックのリスクが高まります。
ウィキペディア
+1
施工タイミング・硬化環境の適正化
冬期にコンクリートを打設・改修する場合、低温・凍結状態・夜間冷却などによる硬化不良・初期クラックを避けるため、適切な養生(保温・凍結防止)を行うこと。
fascrete.com
打設後の温度変動が激しい状態を避け、初期強度が出るまで急激な冷却・凍結を防ぐ対策を講じる。
目地・伸縮ジョイント・クラック制御線の配置
大面積・外壁・屋上などでは、温度収縮・乾燥収縮・温度変化に対して応力を逃がすための目地(コントロールジョイント)を適切に設けることが重要です。
Polycote
+1
接続部位、異素材併用部、開口部縁、サッシまわりなどひずみが大きく出るところには特に配慮。
防水・撥水・シーリング処理
表面の水分浸入を防ぐために、打設後・改修後の防水処理・シーリング・コーティングを適切に行う。特に屋上・外壁では、凍結融解サイクルの被害を抑えるために、浸水・雨水・雪解け水の排水経路・水溜まりを無くすことが重要です。
Port Aggregates
地盤・下地・排水対策
コンクリート構造体が支持している下地・基礎・地盤が凍結・融解で変動しやすい場合、ひび割れや浮き・沈みが起きやすいです。地盤や基礎の凍結帯・排水不良をチェックしておくことも防止につながります。
a1concrete.com
(B) 運用・冬期中の維持管理(お客様側・管理側でできること)
シーズン前(秋~初冬)点検・クリーニング
冬を迎える前に、外壁・屋上・バルコニー・開口部まわり・目地・シーリングの状態を点検し、ひび・剥離・防水層破損・排水不良を確認します。
落ち葉・ゴミ・雪・雨水がたまりやすい状態(排水不良)を解消。たとえば、屋上やバルコニーの「水溜まり」や「凍結残水」がひび割れ誘発因子となります。
Port Aggregates
雪・氷・融雪水対策
冬季の雪・氷の存在は、コンクリート表面を覆い、融雪後の水分が内部に入りやすい状態を作ります。雪を放置しない・水溜まりを作らない・表面を清掃することが重要です。
a1concrete.com
また、融雪剤(塩化物系)の使用はコンクリートを傷める可能性があるため、使用量・種類を検討することが望ましいです。
Port Aggregates
定期的な目視・点検(冬季中も)
冬期中も、雪解け・積雪・凍結・融解のサイクルを経てヒビが広がる可能性があるため、管理者・保守担当者による定期点検(ひび割れ・剥離・ハツリ・浮き・水染み)を実施。
特に高所・足場が難しい外壁・特殊部位(貴社が扱うロープアクセス対象部位)では、ドローン調査・赤外線サーモグラフィー・目視を組み合わせて早期異常発見を図ると効果的です。
早期補修・止水・シーリング補強
点検で発見したひび割れ・漏水痕については、早期に補修・シーリング処理をすることで、冬期間中の悪化を防ぎます。小さい段階のうちに手を入れることで、コストも少なく済みます。
補修後は、該当部位をマーキングして「次の冬までに要再点検」といった管理システムを組むのがおすすめです。
(C) 冬明け後・春先のフォロー
冬の影響(凍結‐融解損傷)の評価
冬が明けたら、雪・氷の影響を受けた外壁・屋上・バルコニー等の「ひび割れ拡大・剥離・スケーリング・浮き沈み・漏水」などの確認を行います。特に、凍結影響によりひびが拡大していないかをチェック。
長期補修計画の検討
冬明け後に点検データを基に、「次のシーズンまでにどこを改修・補強すべきか」「足場/ロープアクセスどちらが合理的か」「外壁仕上げ・防水膜・塗装の更新時期」などを検討します。
ひび割れが多数・深刻な場合は、改修範囲を拡大して大規模修繕計画を練る必要があります。逆に、軽微なひび割れであれば、局所補修+定期監視で十分という判断も可能です。
継続的なモニタリング・記録化
補修後や点検後は、クラックの幅・長さ・進展状況を記録し、「次回点検時との比較」が可能になるようにしておくと、変化を定量的に追え、管理精度が上がります。
弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、
空室対策、不動産管理、地震保険や補助金助成金申請サポート、各専門の士業の御紹介などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしております。
相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
https://meiseitosou.com/contact/