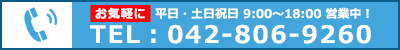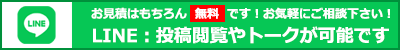ビルやマンションオーナー様のお悩みの中で、「修繕工事をしないといけない状態だけど、現金もないし与信枠でも費用が足りない」「新たに物件を購入して投資に回したいから与信枠を使いたくない」「買取再販で少し綺麗にして売って利幅がほしい」そのような方を多く見受けられます。
そんな方に最適な方法が「現金や与信枠を使用しないで修繕工事費用を最大120回払いにする方法」です。
修繕工事だけでなく、IoTなどのリノベーション工事を行って家賃や資産価値を上げる事にも使用が可能です。
但し、条件としては、宿泊施設や賃貸ビル、マンション、シェアハウスなどで実需向けの建物では使用が出来ません。
カラクリとしては、決算書ではなく部屋の稼働率から、融資金額が決まり、物件を売却した場合には購入者に引き継がれます。
最近ではシェアハウスを始める方にも人気のスキームになります。
弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、
空室対策、不動産管理、地震保険や補助金助成金申請サポート、各専門の士業の御紹介などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしております。
相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
https://meiseitosou.com/contact/
はじめに:大規模修繕工事をめぐる背景
ビルやマンションを所有・運営するうえで、いずれ避けて通れないのが「大規模修繕工事」です。例えば、外壁・屋上防水・給排水設備・エレベーター・電気設備など、建物全体または大部分を対象とした改修がそれにあたります。
mark2002.jp
+3
新東亜工業
+3
shutoken-bm.co.jp
+3
しかしこの種の工事は、規模・範囲・状態・時期等によって数千万円〜1億円以上といった巨額になる場合が多く、オーナー側の資金的・経営的な負担が大きな課題となっています。
shutoken-bm.co.jp
+1
つまるところ、「修繕を行わなければ建物価値・入居状況・安全性などに影響するが、費用が出せない/出すべきタイミングを逃してしまう」というジレンマに直面しているオーナーが少なくありません。本稿では、費用負担が難しいオーナー側から見える課題を整理し、その背景・影響・対応策までを5000字程度で俯瞰します。
課題①:資金の準備不足・資金繰りの逼迫
1‑1 資金積立の仕組みが存在しない、または機能していない
多くのビルオーナーは、日々の運営・修繕対応を「都度対応」で済ませており、将来の大規模修繕に向けた定期的な積立を行えていないケースがあります。分譲マンションの管理組合では「修繕積立金」が日頃から集められていることもありますが、一棟所有の賃貸ビル・商業ビルなどでは、そうした制度が整備されていないことが多く、修繕費用を事後的に手当てせざるを得ないことがあります。
新東亜工業
+1
そのため、いざ大規模修繕の時期がやってきたときに「資金をどうするか」が大きな壁となります。
1‑2 修繕費用そのものの高騰
さらに、修繕にかかる費用のベースが年々上がっている点もオーナーを圧迫しています。たとえば、建築資材や労務費の上昇により、修繕・資本的支出の支出増加を実感しているオーナーが多いという調査があります。
ザイマックス総研
+1
具体的には、ビル・賃貸ビル経営において「支出が増加している」と感じる割合が66%と、収入増の37%を大きく上回っているというデータも出ています。
ザイマックス総研
このようなコスト上昇と、準備されていない積立のギャップが、資金準備不足を招きやすくしています。
1‑3 突発的な支出や追加工事のリスク
多くの大規模修繕では、当初想定していた範囲を超えて追加工事・追加費用が発生することがあります。ある調査では、修繕工事において「追加費用が発生した」と回答した割合が4割を超えています。
マンション管理組合のミカタ
例えば、足場の仮設が予想より手間となった、建物内部の劣化が進んでいた、自然災害の影響で修繕範囲が拡大した、などのケースです。これらは資金準備が十分でないオーナーにとって、まさに「想定外の出費=負担できない/先送りしたい」という判断につながりやすいです。
1‑4 資金繰り・借入負担
資金を自己資金でまかなえない場合、借入(銀行ローンなど)に頼らざるを得ないことがあります。ただし借入を行った場合、返済負担が発生し、その後の賃貸経営収支に影響が出る可能性があります。収入(賃料収入・テナント稼働率)に余裕がない場合、返済負担が重くなり、次の修繕に備えられないという悪循環に陥ることもあります。
1‑5 修繕周期の先送りによる更なる負担
資金が無いために「とりあえず次の大規模修繕を先延ばしにする」オーナーもいます。しかし、専門家は「修繕を先延ばしすることは、コストをさらに増大させるリスクが高い」と指摘しています。
ビル改修.net
+1
劣化が進行すれば、修繕では済まなくなり、交換・更新レベルとなって費用が跳ね上がる可能性があります。また、建物価値や入居状況にも悪影響が出るため、結果的に収支が悪化する恐れがあります。
課題②:建物維持管理・修繕計画の未整備
2‑1 長期修繕計画(LTC・大規模修繕計画)の欠如
理想的には、建物の築年数・劣化状況・設備更新時期などをもとに「何年後にどこをどのように修繕・更新するか」という長期修繕計画を立て、その費用を前もって積立・確保するのが望ましいです。
新東亜工業
+1
しかし、費用負担ができないオーナーは、このような計画を立てていない、あるいは立てても実行できていないケースが多く見られます。計画がないまま「突然工事が必要」になってしまうと、資金確保・工程調整・テナント対応といった管理面でも大きな負荷となります。
2‑2 劣化診断・調査の実施不足
適切な修繕計画を立てるためには、建物・設備の劣化診断/調査を一定周期で行い、現状把握をすることが肝要です。
ビル改修.net
+1
しかし、コストをかけたくない、または忙しさなどから調査を省いてしまうオーナーもいます。その結果、劣化が内部まで進んでいたり、想定外の修繕項目が出てきてしまったりするケースが発生します。これが「修繕費用を負担できない」という状況をさらに悪化させる原因となります。
2‑3 見積もり・施工業者選定の経験・情報不足
「大規模修繕」はオーナーにとって、そう何度も経験するものではないため、経験値が低いケースが多いです。
大阪府大阪市の賃貸管理会社 エスタス管財 –
+1
そのため、提出された見積もりが適正かどうか、工法が妥当かどうかを評価するノウハウに乏しく、提示されたまま契約してしまったり、複数社から相見積もりを取らなかったりすることがあります。特に、低見積もりで手を出して後から追加費用が発生するというパターンもあります。
プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
+1
このような判断ミスが、オーナーの資金負担を増やし、「費用が出せない」という状況を招く一因となっています。
2‑4 意思決定・管理体制の脆弱さ
賃貸ビル・商業ビルオーナーの場合、オーナー個人または法人がすべてを判断・対応しなければならないことがあります。特に複数棟所有の場合や管理を外部委託している場合など、修繕に関する情報の収集・検討・決定が遅れがちです。
また、修繕・更新の時期を「まだ大丈夫」と考えて先延ばしする心理的なハードルも大きく、「やるべきかどうか/いつやるか」の判断が遅れることが、結果的に費用増・資金負担困難に繋がるケースがあります。
課題③:収益構造・経営環境の変化
3‑1 賃料収入・稼働率の低迷
大規模修繕の原資は、通常、日々の運営収入(賃料収入・駐車場収入・テナント収益など)から捻出されるか、資金を準備しておくことで賄われます。しかし近年、テナント需要の変化、空室率の上昇、賃料下落などにより収入面で苦しいオーナーも増えています。たとえば、調査によれば収入増と感じているオーナーは37%に過ぎず、支出増(66%)を大きく下回っています。
ザイマックス総研
収入が十分でない状況では、「修繕のための資金を捻出できない」「修繕を優先できない」という構図ができてしまいます。
3‑2 建物の老朽化による競争力低下
築年数が経過したビルは、設備・構造・省エネ性能・デザイン・機能性などで競争力が低下します。その結果、入居者がつきにくくなったり、賃料を下げざるを得なかったりします。そのような状況下では、修繕・更新へ回せる余力がさらに削がれていきます。
適切な時期に大規模修繕を行うことは、建物の資産価値を維持・向上させ、賃貸収益を安定させるためにも重要ですが、それを後回しにすると「修繕できない→収入減る→修繕できない」という悪循環に入るリスクがあります。
ビル改修.net
3‑3 金利・物価上昇・建設コストの増加
日本国内では建築資材費・労務費・設備費等が上昇傾向にあり、修繕コストの増大を招いています。たとえば、資材価格が毎年5%程度上昇しているというデータもあります。
ザイマックス総研
+1
このようなコスト上昇環境のなかで、収益が伸び悩むオーナーは「収益は横ばいまたは下がっているが、コストだけが上がっている」という厳しい状況に追い込まれやすいです。
課題④:建物価値・入居者対応・社会的責任
4‑1 建物価値の低下・資産の毀損
修繕を適切に実施しないと、建物の外観・機能・安全性・快適性が劣化してしまい、資産価値が下がります。
ビル改修.net
+1
資産価値が下がるということは、将来的に売却・転売・建替・再投資を考えた場合にも不利になります。ビルオーナーにとっては、「修繕を行えない」ことが、長期的な資産運用上の致命的なハンディキャップになりかねません。
4‑2 入居者満足度/テナントとの関係悪化
大規模修繕工事は、足場設置・工事騒音・共用部制限・環境変化など、入居者(テナント)にとって一定の負担を伴います。そのため、工事を行う際には入居者対応が重要です。
新東亜工業
+1
もし修繕を長期間先送りしたり、目立つ劣化を放置したりすれば、「このビルは管理がきちんとされていない」との印象を与え、入居者は退去を検討したり、賃料交渉をしてくる可能性があります。収益面からも大きなマイナス要因です。
4‑3 安全性・法令・社会的責任の問題
例えば外壁タイルの剥落事故や、給排水管の破損、設備故障などが起きてしまえば、入居者・通行人・近隣住民に危害を及ぼすリスクもあります。修繕が未実施・遅延していること自体が、建物オーナーとしてリスクを抱える事態です。
ビル改修.net
また、修繕・改修工事を適切に行わないことが、建築基準法・消防法・建物保全義務などの観点から問題となる場合もあり、社会的・法的責任(コンプライアンス)という視点も無視できません。
課題⑤:タイミング・戦略・実行プロセスの難しさ
5‑1 実施時期の判断ミス・先送りのリスク
いつ修繕を実施するかという「タイミング」は非常に重要です。適切な時期に行えば費用を抑えつつ資産価値を守れますが、逆に「まだ使える」と先延ばしにすると、劣化が進行して修繕費用が大幅に増えることがあります。
ビル改修.net
+1
また、実施時期が遅れることで、施工会社・資材・足場確保・スケジュールの制約などが影響して、工事費用が割高になったり、入居者の退去を余儀なくされたりするケースもあります。
5‑2 工法・範囲・仕様の選定の難しさ
大規模修繕では「どこまで直すか」「どの仕様・工法を採るか」の選定が作業負担/費用負担に直結します。経験値の少ないオーナーほど、施工会社から提示された仕様をそのまま受け入れてしまい、必要以上にコストがかかってしまったという事例もあります。
大阪府大阪市の賃貸管理会社 エスタス管財 –
有効な工法・合理的な範囲・将来を見据えた仕様選定という視点が欠けていると、費用負担が「想定以上」のものになってしまいがちです。
5‑3 テナント調整・運営支障・工事中対応
大規模修繕を実施するとき、入居者(テナント)への事前説明、スケジュール・施工時間帯・騒音・通行制限・共用部利用制限などを調整する必要があります。これらを適切にやらなければ、入居者とのトラブル、工事遅延、賃料減額交渉などが起きる可能性があります。
工事の選定・実行・管理に手間や時間がかかるため、オーナー自身または管理会社のリソースが圧迫され、これが「修繕に手を付けられない」という構図を生むこともあります。
課題⑥:制度・税務・補助金活用などの制度活用不足
6‑1 補助金・助成金・税制優遇の認知・活用不足
大規模修繕・改修工事には、自治体による補助金・助成金、また税制優遇(減価償却・損金算入など)制度がある場合もあります。例えば「省エネ改修」「耐震改修」「バリアフリー化」「外壁劣化対策」などが対象となることがあります。
大阪府大阪市の賃貸管理会社 エスタス管財 –
しかし、費用負担に苦しむオーナーほど「そもそも補助金を知らなかった」「申請準備が手間で諦めた」という状況に陥りがちです。制度を知らない・活用できないことが、資金確保面での機会損失につながります。
6‑2 計画的な経費処理・損金算入・積立制度の設計の難しさ
修繕・改修工事を「経費としてどのように処理するか」「損金算入をどのくらい見込めるか」「積立制度として長期的に資金を確保するためにはどうするか」といった制度設計・税務設計が十分でないと、オーナーのキャッシュフローを圧迫する一因となります。特に個人オーナー・小規模オーナーでは、税務・会計・資金設計に専門的な理解が及ばず、ここに負担を感じることがあります。
課題⑦:心理的・経営的マインドの問題
7‑1 「修繕を後回しにしても大丈夫」という思い込み
建物を所有して間もないオーナーや経験の浅いオーナーのなかには、「まだ大丈夫だろう」「次回でも問題ないだろう」と修繕を先送りしてしまう傾向があります。実際には、劣化は静かに進行するため、見た目が変わらなくても内部に大きな劣化が進んでいることもあります。
ビル改修.net
+1
この心理が、資金を準備できない・修繕の優先順位を下げてしまうという経営上の判断ミスを引き起こし得ます。
7‑2 オーナーとしての建物維持管理意識・時間・リソースの制約
賃貸ビル・商業ビルを所有するオーナーには「本業」が別にあるケースも多く、建物維持管理・修繕工事に関しては専門外・時間が取れない・管理会社任せというパターンも見られます。そのため、情報収集・調査検討・工事管理・フォローアップといったプロセスが疎かになりがちです。先述の「見積もり・工法選定」「長期修繕計画の立案」が結果として不十分になり、「費用を負担できない・できたとしても後手になる」という状態を招きます。
7‑3 リスク回避・淘汰のプレッシャー
特に築年数が古く、収益も低迷している物件オーナーには「修繕をしない→でも収益が下がる/入居者が出る/値引きせざるを得ない」というリスクと、「修繕をして大量出費をする→回収ができるか分からない」というジレンマがあります。このような経営マインドのもとでは、「できれば修繕をしないで済ませたい」という意向が働き、結果として「費用を負担できない(またはしたくない)」という意思決定に繋がることがあります。
対応・改善に向けた視点
上述のように、ビルオーナーが大規模修繕の費用を負担できない・負担に苦しむ背景には、資金面・管理計画面・収益構造面・制度活用面・マインド面と、多様な要因が絡み合っています。以下では、オーナーとして検討すべき対応・改善の視点を整理します。
長期修繕計画(LTC)の策定・見直し
建物の築年数・設備更新時期・劣化状況を踏まえ、10年・20年・30年先を見据えた修繕計画を作成しましょう。必要であれば専門家(建築士・修繕コンサルタント)による劣化診断を実施したうえで、「いつ・どこを・どのくらい」修繕すべきかを明確にすることが有効です。
shutoken-bm.co.jp
+1
定期的な劣化診断・現状調査を実施
調査を怠ると、想定外の劣化・追加工事が発生してコスト増に直結します。足場仮設前に下地を確認する、設備の内部劣化を把握するなど、先手を打つ姿勢が重要です。
マンション管理組合のミカタ
資金確保・積立制度の検討
修繕を行うタイミングまでに必要資金を準備できるよう、毎年一定額を「修繕準備金」として積み立てることを検討します。また、収益が厳しい年であっても、将来的な出費を見据えて少額でも積立を続けることが安心につながります。
補助金・助成金・税制優遇制度を調査・活用
自治体・国の制度で「耐震改修」「省エネ改修」「外壁改修」などに助成がある場合があります。これらを活用できれば資金負担軽減に繋がります。制度適用要件・申請手続きは少々手間ですが、将来的な支出削減の観点から有効です。
見積もりの複数取得・相見積もりの徹底
施工業者・見積もり内容・工法・仕様を複数社から比較検討することで、適正な価格で工事を発注する可能性が高まります。経験の少ないオーナーほどこのプロセスを怠りがちですが、コスト削減の観点から実践する価値があります。
プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES
+1
工事の範囲・時期選定・工法の戦略的な検討
例えば「足場を使わない工法(無足場工法)」を検討する、「複数回に分けてやるべき工事を一括化して足場コストを節約する」など、工法・時期を戦略的に設計することが重要です。
大阪府大阪市の賃貸管理会社 エスタス管財 –
テナント・入居者対応・コミュニケーションの強化
修繕を行う際、入居者への影響を配慮し、事前説明・スケジュール共有・安心感の提供を行うことが、入居維持・賃料維持に繋がります。修繕を行わないことのコストだけでなく、修繕を適切に実施することで得られる収益安定性を意識することも大切です。
収益構造の再点検・収入改善施策の併用
収益が低迷していて修繕費用が出せないという状況では、修繕だけを見るのではなく、「収入改善(テナント募集・賃料改善・稼働率向上)」「運営コスト見直し」なども並行して検討すべきです。収益の余力があってこそ、修繕への備えも可能となります。
先延ばしにしない意思決定マインドの醸成
「もう少し後で」「次の機会に」と修繕を後回しにする判断は、長期的には大きなコストを招く可能性があります。早めの検討・準備・実行というマインドを持つことが、オーナーとしての経営姿勢として望まれます。