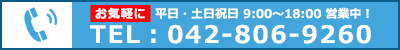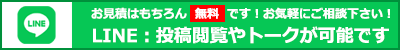2025年の4月に法改正がありました。
弊社のお客様でもあるビルオーナー様からも、お問合せがあったので共有させて頂きます。
1. 法改正の背景と目的
2025年4月1日に施行された二つの法改正は、単なるルールの変更ではありません。国が2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)という大きな目標に向けて進める住宅政策の一環であり、建物の安全性と省エネ性能を同時に底上げする狙いがあります。
これまでの日本の住宅市場では、新築住宅は高性能化が進んでいる一方、中古住宅や築古物件は性能が低いまま流通するケースが多く見られました。そのため、中古住宅の価値が著しく下がりやすく、ストック活用が進まないという課題がありました。
また、省エネ性能を高めるために断熱材を厚くしたり、太陽光パネルを搭載することは建物の重量増加につながります。重量が増えた建物に対して十分な耐震性や構造安全性が確保されていない場合、大地震時のリスクが高まります。こうした背景から、構造面の審査も強化されたのです。
2. 建築物省エネ法の改正内容
2-1. 適合義務化の対象が「全ての新築」に拡大
改正前までは、住宅については300㎡以上の建築物のみ省エネ基準への適合義務が課せられていました。しかし、2025年4月以降は原則として全ての新築建物が対象となります。
これにより、木造の小規模住宅でも、建築主は省エネ基準を満たす計画を立て、建築確認の段階で証明する必要があります。具体的には以下の性能が求められます。
外皮性能(断熱・気密性能):UA値(外皮平均熱貫流率)、ηAC値(冷房期日射取得率)など
一次エネルギー消費量:冷暖房・給湯・換気・照明・家電等の総エネルギー効率
2-2. 中古住宅への間接的影響
この改正は新築住宅が対象ですが、中古住宅市場にも波及します。理由は簡単で、省エネ基準に適合していない築古物件が市場で敬遠される傾向が強まるからです。
将来的には以下の可能性も指摘されています。
省エネ未対応物件は住宅ローンの審査で不利になる
補助金や税制優遇が省エネ適合住宅に集中する
資産価値が相対的に低下
3. 建築基準法改正(4号特例縮小)
3-1. 4号特例とは
これまで、木造2階建てや延べ面積500㎡以下などの小規模住宅は、建築確認申請の際に構造計算書や省エネ性能の詳細な審査が免除されていました。これが「4号特例」です。
3-2. 改正で審査強化
2025年4月以降は、この特例の対象が縮小され、木造2階建て住宅などでも構造安全性の審査が必須になりました。
主要構造部(柱・梁・耐力壁等)の安全性を確認
増改築・大規模リフォームでも確認申請が必要になるケースが増加
3-3. 中古戸建てへの影響
大規模なリフォームや増築を行う際、建物全体が現行の新基準に適合していることを証明する必要が出てきました。
特に築古住宅では当時の設計図面や構造計算書が残っていないことが多く、適合性を証明できないケースが増えると考えられます。その場合、事実上リフォームや増築ができないという問題が発生します。
4. 「再建築不可物件」への深刻な打撃
接道義務を満たしていない土地などでは、建て替えができない「再建築不可物件」となります。これまでは建て替えできない代わりに、建築確認申請が不要な範囲での大規模リノベーションを行うことで資産価値を維持してきました。
しかし今回の法改正で、リノベーションでも建築確認申請が必要になるケースが増加し、再建築不可物件は手の施しようがなくなる可能性が高まりました。
これは資産価値の暴落につながりかねません。今後、中古市場では再建築不可物件が大幅に評価を下げるリスクが高いといえます。
5. 今後の中古住宅市場の動向
省エネ性能が高い住宅の評価が高まる
書類(設計図面・構造計算書)が揃っていない物件は敬遠される
再建築不可物件の市場価値は下落傾向が加速
投資用としての築古戸建ての扱いが難しくなる
6. 私たちが取るべき対策
6-1. 中古住宅をこれから買う人
「再建築可能か」を必ず確認
建築時の設計図面・構造資料が揃っているかを確認
ホームインスペクション(住宅診断)を活用
省エネ性能の低い住宅は購入後の改修費用も視野に入れる
6-2. すでに物件を所有している人
再建築不可かどうかの確認を早急に行う
図面や証明書類が揃っていない場合は、早めに専門家へ相談
大規模リフォームを検討している場合は、適合証明の可否を調べる
場合によっては売却も視野に入れ、今後の資産戦略を立てる
7. 専門家への相談が必須
不動産の価値は、法律改正や市場の動きによって大きく変わります。今回の改正はその典型例です。
建築士や不動産エージェントに相談して現状を把握
将来的な価値の目減りを防ぐための対策を検討
特に「再建築不可物件」や「築古住宅の大規模リフォーム」を検討している場合は、早めのアクションが必要です。
弊社のように、建築士資格を持つエージェントが在籍する会社であれば、法律・構造・資産価値の三方向から適切なアドバイスを受けることができます。
まとめ
2025年4月1日に施行された二つの法改正は、新築住宅だけでなく中古住宅市場にも大きな影響を与えます。特に再建築不可物件や築古住宅を所有・購入予定の方は、資産価値の下落やリフォームの制限といった深刻なリスクに備える必要があります。
まずは「自分の物件がどのような状況にあるのか」を正確に把握することが第一歩です。設計図面や建築時の資料を揃え、専門家に相談することで将来の不安を減らすことができます。
弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、
空室対策、不動産管理、地震保険や補助金助成金申請サポート、各専門の士業の御紹介などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしております。
相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。