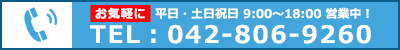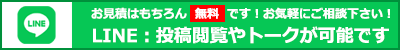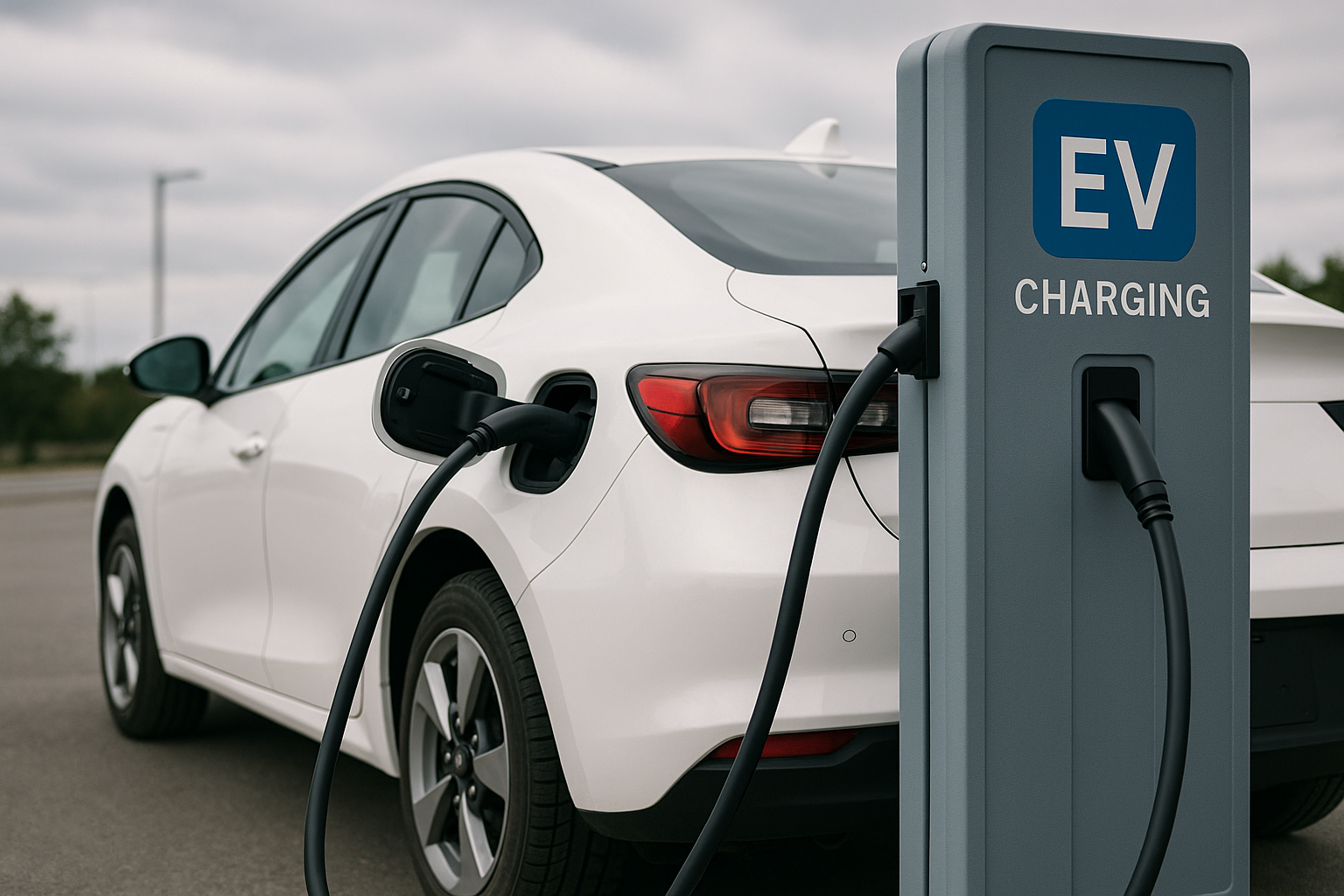
東京都に限り2026年の3月まで、EV車用の充電器の設置に関する補助金が適用されています。
設置も維持費も電気代も0円で行えるため、空室対策にも相性が良いです。
東京都以外では今年度の募集が8月で終わってしまっているので来年度の予算が出れば、春先早々に申し込みをした方が良さそうです。
弊社でも補助金申請から設置まで一気通貫で行える会社を御紹介出来ますので、お気軽にお問合せ下さい。
■政策として広げようとしているEVについても、まとめてみました。
気候変動対策や脱炭素政策が世界的に強まる中、日本でも「EV化(電動車化)」は重要な柱の一つです。EV普及には「車本体の価格」「航続距離・バッテリー性能」「充電インフラ」の整備が鍵ですが、中でも充電器(普通充電/急速充電)の設置数・利便性はユーザーが EV に乗るかどうかを左右する重大な要素です。
以下、まず現状を整理し、その上で将来の需要見込み、環境への影響、課題とその対策を述べます。
現状データと政策目標
現在の充電インフラの状況
日本の EV 充電器整備状況にはこうしたポイントがあります:
-
2024年3月時点で、全国に 約4万口 の充電器が設置されており、そのうち普通充電器が約 3万口、急速充電器が約 1万口。 EVスタートビズ+2自然電力株式会社+2
-
普通充電器は主に集合住宅、商業施設、公共施設など、日常生活で使いやすい場所に増設が進んでいます。急速充電器も、道路沿いや高速道、道の駅、コンビニなどでの整備が強化されています。 Myプラゴ |充電予約で、EVライフをもっと自由に。+3CHAdeMO+3ギグワークス+3
政策の目標
政府(経済産業省等)は、充電インフラ整備について次のような目標を掲げています:
-
「グリーン成長戦略」(2021年)では、2030年までに公共用急速充電器を含めた充電インフラを 15万基 設置すること。 自然電力株式会社+2新電力ネット+2
-
その後、「充電インフラ整備促進に向けた指針」の見直しで、「口(charging outlet)」単位での目標を 30万口 に引き上げ。普通・急速を含めた全体数をこの単位で増やすことが意図されています。 EVスタートビズ+1
利用率・普及率などの背景
-
2024年時点での EV の普及率は、乗用車販売に占める割合で 約1.4% 程度と報告されており、まだごく初期段階。 EVスタートビズ+1
-
EV を使ったことがない/使ってみたいが不安がある、という声がアンケートで散見され、「充電の不安」「インフラがどこまで整っているか」の疑問が普及の阻害要因とされています。 経済産業省+1
将来の需要見込み
この現状と政策目標をもとに、今後の充電器需要を以下の要素で見込むことができます。
| 要素 | 内容 | 影響(需要増への寄与) |
|---|---|---|
| EV普及の加速 | 自動車メーカーの EV 車種拡充、価格低下、補助金・税制優遇。消費者の関心上昇。 | 車台数が増えれば、それに比例して充電器も増加必至。特に普通充電器は家庭・集合住宅・職場などでの設置が急務。急速充電器も「長距離移動時」「公共・商用利用」での需要。 |
| 政策による後押し | 上記 2030年目標、補助金制度、自治体支援など。土地利用規制・電力供給インフラの整備も含む。 | 政府の目標があることで、企業・地方自治体が事業を検討しやすくなる。予算がつけば設置コストが下がる。 |
| 地域差/用途別差 | 都市部 vs 農村部、住宅地 vs 高速道路沿い vs 観光地等での需要の偏り。普通充電 vs 急速充電。 | 都市部や交通インフラが整っている地域でまず需要が高く、地方・山間部でも目的地型充電(道の駅など)の充実が見込まれる。急速充電はコスト・電力供給制約もあるが需要が大きい。 |
| 技術進歩 | バッテリー容量の向上、充電時間短縮、充電器コスト低下、出力アップなど。 | 充電時間が短くなれば、「充電すること自体のコスト(時間・待ち)」が減り、利用が拡大。急速充電器出力が上がれば少ない台数でのインフラ網構築も可能。 |
これらを総合すると、2030年にかけては EV 車両の数が現状比で数倍~十数倍に増加する見込みであり、これを支えるために充電器(普通+急速)の設置口数も大きく伸びる必要があります。
具体的に言うと、
-
普通充電器(主に住宅・オフィス・商業施設等):数十万口規模になる可能性が高い。
-
急速充電器(公共・長距離用途・商用車含む):現状約1万口程度から、2030年には少なくとも数万口に拡大。
政策目標の 30万口というのは、このような将来需要を見越したものです。つまり「30万口」が達成できるかどうかが、普及加速のカギと言えるでしょう。
環境への好影響
EV と充電インフラの増強による環境面でのメリットを、定量的・質的に整理します。
CO₂削減
-
内燃機関車(ガソリン・ディーゼル車)に比べ、走行中に排出される CO₂ と大気汚染物質(NOx、PMなど)がゼロであることが EV の大きな特徴。
-
ただし、発電方法に依存します。電力が再生可能エネルギーや低炭素電源から供給されれば、CO₂ 削減効果は非常に大きい。逆に化石燃料発電が主であれば、その分 CO₂ 排出も出ますが、それでも内燃車よりは改善が図れるケースが多い。 丸紅電機+2arXiv+2
-
発電と電力系統の混雑を抑えるため、夜間充電やピークシフト、スマート充電(充電時間を管理・調整する仕組み)の導入が鍵となる。これにより電力網への負荷を低減すると同時に、電源構成が再エネ中心でない地域でも CO₂ 集約度を下げやすくなる。 丸紅電機+1
大気汚染・健康被害の軽減
-
都市部での排ガス(NOx、PM2.5など)の発生が減る。これが呼吸器・心疾患などの健康被害を抑える効果。特に近年、道路交通からの大気汚染が住民に与える影響が注目されており、EV による改善が期待される。
-
また騒音公害の軽減(特にエンジン音・振動が小さい EV)も都市環境の快適性を向上させる要素。
エネルギー効率・エネルギー安全保障
-
EV は電動モーターの効率が高いため、エネルギー変換効率の観点で内燃機関より優れています。燃料として輸入石油への依存が減ることで、エネルギー安全保障の観点でのメリットもある。
-
また、再生可能エネルギー発電と組み合わせて充電インフラを運用すれば、「グリッドの蓄電機能」のような役割も持てる(たとえば車両から電力を戻す Vehicle-to-Grid/Bidirectional Charging の可能性)という議論も進んでいます。
ライフサイクルでの環境コスト
-
車両の製造時・バッテリー製造時には多くの資源・エネルギー・CO₂ がかかります。バッテリーの採掘・製造・輸送、そして廃棄・リサイクルまで含めたライフサイクルアセスメント(LCA)の視点が重要です。EV が真に脱炭素に寄与するには、これら製造段階や電池リサイクル・素材調達の改善が求められます。
-
また、急速充電を頻繁に行うことはバッテリーの劣化を促進する可能性があり、適切な充電管理が求められます。
図解構成案
文章だけでなく図解を交えることで、需要と環境影響がより分かりやすくなるでしょう。以下は図解案です:
-
充電器数の推移と目標
-
横軸:年(例 2020, 2025, 2030)
-
縦軸:充電器設置数(普通充電器口数、急速充電器口数など二本線)
-
真の線で過去実績、破線で政策目標(30万口など)
-
-
** EV 普及率の予測と充電器必要数のシナリオ比較**
-
数シナリオ(低普及シナリオ、中位普及シナリオ、高普及シナリオ)
-
各シナリオで必要となる充電器口数(普通/急速)、設置コスト、電力需要の予測
-
-
CO₂ 排出削減の見込み
-
内燃車使用時 vs EV 使用時の CO₂ 排出量の比較
-
発電構成による差異(再エネ率が低い/高い場合)
-
-
電力系統への影響とピーク負荷管理
-
日中・夜間の電力需要グラフ
-
EV充電による追加負荷のピークシフト例
-
スマート充電や V2G 等の導入でピークがどう抑えられるか
-
-
環境・健康便益の分布図
-
都市部 vs 地方部での大気汚染改善予測
-
健康被害(呼吸器疾患など)の減少推定データ(可能なら)
-
課題と対策
需要・好影響が見込まれる一方で、実際に普及を進めるには複数の課題があります。以下、主な課題とそれに対する対策案。
| 課題 | 内容 | 対策案 |
|---|---|---|
| 用地・場所の確保 | 駐車スペースが限られる、土地利用制約、景観・自治体規制など | 商業施設・施設駐車場との協業、自治体による規制緩和、公共施設での設置を促進、既存駐車場の活用 |
| 電力供給インフラ | 電力の引き込み容量、変圧設備などが不足している地域がある。急速充電同時使用時のピーク負荷。 | 電力会社と協調した設備強化、送配電網の整備、ピークシフト充電・オフピーク充電インセンティブ、蓄電設備との併用、再エネ電源との調整 |
| コスト(設置コスト・維持コスト) | 高出力充電器は導入コストが高く、維持管理も必要。普通充電器でも土地・電気代・インフラ改修などでコストがかかる。 | 補助金制度・税制優遇、設置コストの分散モデル(共同設置)、民間事業者参加の促進、標準化によるコスト低減、充電器のモジュール化 |
| 規格・インターフェースの統一 | 車種による充電方式やプラグ形状が異なること、相互運用性の問題。 | 国際規格・国内標準の調整、プラグ変換アダプタの普及、統一型急速充電器の普及、規制による標準化支援 |
| ユーザーの利用意識・情報不足 | 充電場所や料金体系・充電時間などへの不安、どこで充電できるか分かりにくい、充電インフラの信頼性・使い勝手への懸念 | 地図アプリ/充電ステーション検索の整備、利用者向け情報公開、充電料金の透明性、試乗キャンペーン・啓発活動、ユーザーからのフィードバックを反映 |
| バッテリー・発電側の課題 | バッテリーの原材料・製造コスト・リサイクル問題、発電側での再エネ率・発電コスト・電力供給の安定性 | リサイクル技術の強化、バッテリーの長寿命化・コスト低減、発電の脱炭素化、再エネ導入促進、蓄電池との併用、分散型電源の活用、スマートグリッド技術の導入 |
見通し:2030~2040年
これらを踏まえて、2030年~2040年の中期~長期での見通しを整理します。
| 年 | EV 普及率予想 | 必要な充電器口数(累積) | 主な設置場所・タイプ | 環境・社会への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 2030年 | 普通乗用車販売台数での EV 比率が 20~30% 程度になるシナリオが多く議論されている(政府・自治体・自動車メーカーの計画による) | 政府目標の 30万口 は、おそらくこのあたりを満たすか若干上回るレベルが必要 → 普通充電器は25万口+、急速充電器はそのうち数万口の割合 | 商業施設、集合住宅・オフィス・公共施設ほか高速道路・観光地・道の駅などが急速充電器での重点地点 | CO₂排出の大幅削減、大気汚染の改善、都市の交通騒音低減、エネルギー輸入依存の軽減 等が進む。電力系統・再エネとの連携が鍵。 |
| 2040年 | EV 車両が全車(あるいは多くの車種で)大きな割合を占めるフェーズへ(ハイブリッド含むが、内燃のみ車がかなり限定される状況) | 普通充電器・急速充電器を含めて 数十万口~100万口 規模が想定される。特に地方・観光地・夜間・宿泊施設での充電器需要が拡大。 | 車両に搭載電池容量が増すことで、一回の充電での走行距離が伸び、急速充電より普通充電を主に使う生活パターンが多くなる。V2G,双方向の充電/放電が一部導入される。 | 発電構成が再エネ中心になることで、EV化の環境メリットが最大化。都市・地方における空気質・健康指標での改善が顕著に。再エネ+電池蓄電・スマートグリッドによる総合的なエネルギー効率向上。社会コスト(環境被害・健康被害・資源輸入など)の削減が期待される。 |
図解イメージ案(文字による擬似説明)
以下に図解を言葉で表したものをお見せします(実際に図を描く際の構成案です)。
図1:EV普及率と充電器設置数の推移
-
普通充電器(普通口数)・急速充電器(急速口数)の2本の推移線
-
政策目標としての 2025~2030 年の目標点(例 30万口など)
図2: CO₂ 排出と再エネ率の関係
-
再エネ率が高まるほど、EV の CO₂ 排出量が著しく下がることを可視化
図3:電力負荷ピーク vs スマート充電の導入
-
急速充電や多数の EV が一斉に充電を始める夕方などにピークが出る
-
スマート充電・オフピーク充電促進でピークを平準化できる様子
日本における予測シナリオ例
具体的な数値シナリオを仮定すると、以下のようなものがあります。
| シナリオ | EV普及率(乗用車) | 普通充電器口数 | 急速充電器口数 | 主な課題 |
|---|---|---|---|---|
| 「政策+技術順調」シナリオ | 2030年に 25‑30% | 普通充電器:25‑40万口 | 急速充電器:5‑10万口 | 電力供給強化、設置コスト、設置場所の確保、バッテリーや発電の再エネ比率の改善 |
| 「控えめ」シナリオ | 普及進むが 2030年で 15‑20% | 普通充電器:15‑25万口 | 急速充電器:3‑6万口 | 補助制度・政策が足りない、規格の混在、地方での設置遅れなど |
| 「高度な普及・長期」シナリオ(2040年頃) | EV/PHEV/燃料電池車など含めてかなりのシェアに | 普通充電器:50‑80万口規模 | 急速充電器:10‑20万口規模(必要出力含む) | インフラ維持・更新、バッテリーの劣化管理、リサイクル体制、発電側の脱炭素化などが成功していることが前提 |
結論と総括
日本における EV 充電器の需要は、今後数年〜10年で 非常に大きく伸びることがほぼ確実です。政策目標(30万口など)も、その伸びを前提として設定されていますし、多くの自動車メーカー・地方自治体も EV 普及を前提にインフラ整備計画を立てています。
また、環境への影響は EV と充電インフラの改善が進めば、「内燃車に比べて CO₂ や大気汚染の実質的な削減」が可能です。特に都市部での大気質改善・健康被害軽減・静音性の向上などは市民生活の質を高めます。
弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、
空室対策、不動産管理、地震保険や補助金助成金申請サポート、各専門の士業の御紹介などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしております。
相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
https://meiseitosou.com/contact/